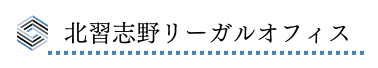配偶者と子どもに最低限度の相続分を保証したもの
遺言の内容は、遺言者がだれに何を引き継ぐのかを自由に決めることができます。
遺言で特定の相続人のみが相続財産を引き継ぐことを決めることもできますがそうすると、他の相続人の相続時に引き継ぐ財産への期待を保護することができません。
また、被相続人の死亡後の相続人の生活を保障することができません。
そこで、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人から遺産相続する財産のうち一定の割合で
相続財産を確保できることを保証したものが遺留分です。


被相続人による贈与や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、財産の返還を請求することができます。
この遺留分を侵害している人への意思表示を『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』といいます。
例えば、父が「妻に全財産を相続させる」という遺言書を残して亡くなった場合、もちろん遺言の内容は有効です。
ただ、子どもは遺言がなければ遺産相続する財産の2分の1を相続できるハズだったにも関わらず遺言があるために相続するものが何もなくなってしまいます。
このような場合、子どもの最低限の相続財産を確保するため、母に対して遺留分減殺請求権を行使することができます。
遺留分は放棄をすることができます。
遺留分の放棄は、相続の放棄ではありませんので、遺留分を放棄しても相続人であることには変わりはありません。
また、必ず遺留分の権利を請求しなければいけないわけではありませんので
請求せずに時間が経てば時効により権利が消滅して、事実上の遺留分を放棄したことになります。
遺留分の権利を有する人(遺留分権利者)
第3順位の法定相続人(兄弟姉妹)以外の法定相続人が、遺留分権利者です。
よって、配偶者、第1順位の法定相続人の子どもが遺留分権利者となります。
被相続人の死亡前に子どもが死亡している場合は、子どもの代襲相続人である孫が遺留分権利者となります。
第1順位の法定相続人がいない場合は、配偶者と第2順位の法定相続人(父母)が遺留分権利者になります。
第3順位の兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、ケースによって異なり、すこし複雑です。
遺留分権利者が複数いる場合の1人あたりの個別的な遺留分の割合(遺留分率)は
①全体の遺留分の対象となる割合に、②それぞれの遺留分権利者の法定相続分の割合をかける方法で算出します。
相続人の協議でこの割合を変更することはできません。
①全体の遺留分の対象となる割合
第2順位の相続人(直系尊属)のみのときは、「遺産相続する財産の3分の1」です。
その他の場合には、「遺産相続する財産の2分の1」です。
以下は、それぞれの具体例です。
被相続人の財産の2分の1が遺留分の対象となります。
被相続人の財産の2分の1が遺留分の対象となります。
被相続人の財産の3分の1が遺留分の対象となります。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分を請求することはできません。
- 相続人が配偶者Aと子どもBCDのときの場合の遺留分を考えてみましょう。
-
(1)配偶者と子どもが相続人の場合に該当します。
遺留分対象割合の2分の1に各相続人の法定相続分をかけた割合が
それぞれの遺留分率となります。・配偶者の遺留分率 ⇒ 1/4
〔1/2(遺留分対象割合)×1/2(法定相続分)〕
・子どもAの遺留分率 ⇒ 1/12
〔1/2(遺留分対象割合)×1/6(法定相続分)〕・子どもBの遺留分率 ⇒ 1/12
〔1/2(遺留分対象割合)×1/6(法定相続分)〕・子どもCの遺留分率 ⇒ 1/12
〔1/2(遺留分対象割合)×1/6(法定相続分)〕
遺留分の権利(遺留分減殺請求権)を行使するには
遺留分を侵害するような遺贈や贈与は、当然に無効となるものではありません。
遺留分を有する人(遺留分権利者)が、遺留分減殺請求権を行使したときに
遺留分を侵害された限度において確定的に遺贈・贈与が減殺されることになります。
まず遺贈から減殺し、それでも遺留分に満たないときは、贈与を減殺します。
行使の方法は、裁判ではなく口頭でも認められていますが、一般的には配達証明付き内容証明郵便で行います。
遺留分減殺請求権をするときは、時効によって権利行使ができないこともあるので注意が必要です。
遺留分の放棄
相続の開始前に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可があればすることができます。
一方、相続の開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得ずに自由にすることができます。
共同相続人のうちの1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響することはありません。
たとえば、相続人が配偶者Aと子どものBCDの場合、Aが遺留分を放棄しても子どものBCDの遺留分はそれぞれ12分の1のままです。
なお、遺留分の放棄をしても相続の放棄をしたことにはなりませんので
遺留分の放棄をした人であっても相続人であることは変わりません。
時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から
1年間権利を行使しないときは、時効により消滅しますので、行使することはできません。
相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時とは
贈与や遺贈があったことを単に知ることだけではなく、それが遺留分を侵害していることも知った時のことをいいます。
また、相続開始のときから10年を経過したときも遺留分減殺請求権は消滅しますので
行使することはできません。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝