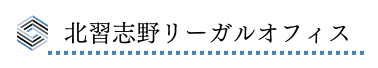任意後見の流れ
任意後見の開始から終了までのおおまかな流れは下記のとおりです。
任意後見契約とは、本人の判断能力が十分にあるときに、本人が希望する人を代理人(任意後見受任者)として選んでおいて、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで開始する契約のことをいいます。
この任意後見契約は公正証書でする必要があります。
実際に、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約がスタートします。
※任意後見受任者(任意後見人)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。
家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立ては、次の人がおこないます。
なお、本人以外の申立ての場合は、本人の同意が必要になります。
・本人
・配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者
任意後見監督人が選任されてると、任意後見受任者は任意後見人となります。
そして、任意後見監督人の監督のもとで、任意後見契約の内容にしたがって後見事務(身上監護・財産管理)を行います。
身上監護・財産管理については、こちらをご覧ください。
任意後見人は、任意後見監督人に後見事務の報告をします。
任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督し、任意後見人の後見事務を家庭裁判所に報告します。
任意後見契約は、次の4つの理由によって終了します。
・本人または任意後見人が死亡すること
・任意後見人が解任されること
・任意後見契約が解約されること
・成年後見等の法定後見が開始されること
任意後見契約の役割
任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに本人を支援する役割を果たします。
そのため、本人は契約をするときに、十分な判断能力を有している必要があります。
任意後見契約がどういうものかを判断できない程度に認知症が進んでしまっている場合は、任意後見契約を締結することができず、法定後見を利用することになります。
本人の判断能力の衰えがはじまっていても、契約をする意思能力があって、契約内容を理解することができれば、任意後見契約を締結することができます。この場合は判断能力の低下がはじまっているため、すぐに任意後見をスタートさせる必要があり、「即効型の任意後見契約」と言われています。
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります。
任意後見は、法定後見と異なり、判断能力低下した後の面倒をみてもらう後見人(「任意後見受任者」といいます)を自分で選んでおくことができます。
※法定後見の場合は、家庭裁判所が選任します。その際、申立時に後見人候補者を記載しても、必ずしもその人が後見人となるわけではありません。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝