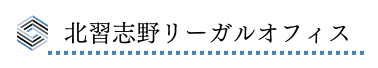成年後見
成年後見人の権限
成年後見人のできること(主な権限)は下記の3点です。
①代理権 成年被後見人の財産に関する法律行為をすること
②取消権 成年被後見人の行った法律行為を取り消すこと
③財産管理権 成年被後見人の財産を管理すること
財産管理・身上看護とは?
財産管理
財産管理とは、成年後見人が、法律行為の代理権を行使して契約を締結したり、預貯金や収入支出の管理等をすることで被後見人の財産上の利益を保護することです。そのために、成年後見人には、法律行為の代理権・取消権が与えられています。
①預貯金の管理
成年後見人は、被後見人の預貯金の管理をします。
現金であれば、現金出納帳をつけて管理し、被後見人名義の預金は、金融機関へ成年後見制度に関する届出書を提出して、就任の届出をします。
預金が1,000万円を超える場合など、必要であればペイオフ対策をします。
②収入支出の管理
年金の収入がある場合は、国民年金・厚生年金等の各種年金の受給のための手続きを行います。被後見人がアパートなどを所有していて賃料収入があるときは、賃料の受領などをします。
③証券類等の金融商品の管理
証券会社などに成年後見制度に関する届出書を提出して、就任の届出をします。
身上看護
身上看護とは、成年後見人が、介護サービス契約・老人施設の入所契約等の被後見人の身上面での法律行為を行い、被後見人の生活、療養看護を保護することです。
※介護行為などの事実行為をすることは成年後見人の権限に含まれません。
①医療に関する契約
医療に関する契約を締結したり、医療費を支払ったり、病院が適切に義務を履行しているかなどの監視等を行います。なお、手術などの医療行為を受けること自体は、本人の同意を得なければなりません。
②介護等に関する契約
介護保険法に基づく介護保険の認定申請・不服申し立て・ケアプランの検討・介護サービス契約の締結・介護費用の支払いなどを行うことになります
なお、介護行為等の事実行為は含まれません。
③住まいに関する契約
被後見人の住居が借地・借家であれば、更新料や家賃の支払い等をします。被後見人の持ち家のときは、固定資産税などの税金の支払いや必要であればスロープを作る・手すりをつけるといった増改築の契約も必要になります。
④施設に関する契約(施設の入退所)
施設の入所契約の締結・費用の支払い・入所中の施設訪問・施設側のサービス内容の監視を行う。
⑤教育・リハビリに関する契約
学習教育やリハビリ施設の情報収集や入学・施設入所などの契約の締結、学費・施設利用料の支払い等を行います。
身上配慮義務
成年後見人は、被後見人の生活・療養看護・財産管理に関する職務を行うときは、被後見人の意思を尊重し、被後見人の心身の状態・生活状況に配慮しなければいけません。これは身上監護の面だけでなく、財産管理の面でも同様です。
本人の資格制限
①資格制限
「後見開始の審判」、「保佐開始の審判」を受けると、本人の資格が制限されます。
「補助開始の審判」については、資格制限を受けることはありません。
なお、資格制限は後見や保佐の審判を受けた人だけなので、後見や保佐に相当する判断能力だっとしても、審判を受けていない場合は資格制限の対象にはなりません。
後見開始の審判を受けたときの資格制限
・本人の印鑑登録が抹消されます。
後見開始の審判、保佐開始の審判を受けたときの資格制限
・株式会社の取締役や監査役などの会社役員に就任することができません。
・公務員などの地位を失います。
・医師、弁護士、司法書士などの資格を失います。
補助開始の審判を受けたときの資格制限
ありません。
Q、成年後見制度を利用すると、戸籍にそのことが記載されますか?
A、かつての成年後見制度は、禁治産・準禁治産制度というものでこのときは戸籍にそのことが記載されていました。しかし、2000年4月から禁治産・準禁治産制度が成年後見制度に変わり、戸籍には記載されなくなりました。
新たに後見登記の制度ができ、成年後見制度の利用の有無が登記されることになります。この登記は、誰でも取得することができるものではなく、一定の利害関係人のみが取得することができます。
Q、成年後見制度を利用すると、選挙で投票することができなくなりますか?
A、これまでは、成年被後見人については、選挙権が制限されていました。しかし、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が平成25年5月27日に成立したことにより、平成25年7月以降の選挙からは成年被後見人である人も選挙で投票することができるようになりました。
保佐・補助の制度を利用している本人は、従前どおり選挙での投票をすることができます。
②財産に関する権限の制限
②財産に関する権限の制限
申立ての手続き
成年後見の申し立ての手続き
成年後見の場合、家庭裁判所へ後見開始の申立書と添付書類を提出します。
①家庭裁判所への申立て
【申立人】
・本人、本人の配偶者や4親等内の親族
・検察官
・市町村長
【提出書類】
・申立書
・診断書および診断書付票
・親族関係図
・本人の親族の同意書
・後見人等候補者事情説明書
※候補者が親族の場合
・本人の収支予定表
・本人の財産目録
・申立人の書類(戸籍謄本)
・本人の書類(戸籍謄本・住民票・後見の登記事項証明書)
・成年被後見人候補者の書類(住民票)
・本人の財産に関する書類(預貯金・不動産・収入内容などの資料のコピー)
【費用】(合計8,050円~108,050円程度)
・収入印紙 3,400円
※申立用800円+登記用2,600円
・郵便切手 4,650円
・鑑定料 50,000~100,000円程度
※家庭裁判所の判断で、必要により鑑定を行います。
※予納金の納付
鑑定を行う場合、あらかじめ鑑定費用を家庭裁判所に納める必要があります。約10万円程度が鑑定費用です。
②家庭裁判所の調査官による事実調査
本人の自己決定権の尊重に基づき、本人の陳述を聴き、成年後見人候補者についての本人を意向を確認します。
成年後見人候補者については、後見人としての適格性や本人との関係を調査をします。
③精神鑑定
医師による本人の精神状態についての鑑定がされます。
提出した医師の診断書から、本人が植物状態であることなどにより、明らかに鑑定が不要な場合は、鑑定は行われません。
④審判
本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合には、後見開始の審判がされます。
⑤審判の告知と通知
後見開始の審判は、成年被後見人となる本人へ「通知」がされます。
申立人と成年後見人に選任される人には、「告知」をします。
⑥後見の開始
後見開始の審判は、成年後見人に選任される人に告知がされてから2週間を経過すると確定して効力が発生します。
⑦後見登記
後見開始の審判が確定した後、裁判所書記官によって後見の登記が嘱託されます。
後見の終了
後見の終了原因と終了の手続き
◆後見終了の原因
◆終了手続き(本人の死亡の場合)
後見終了の原因
後見人等は、たとえ遺産分割の協議や不動産の売却をすることをきっかけに成年後見制度を利用した場合でも、原則として本人が死亡するか、判断能力が回復するまで職務を務めます。
成年後見人等を自由に辞任するにはできず、正当な事由(後見人が仕事の都合で遠隔地に転居など)があって家庭裁判所の許可を得れば辞任することができます。
また、後見人であることがふさわしくないような不正行為等があれば、家庭裁判所は申立てや職権により、後見人を解任します。
終了手続き(本人の死亡の場合)
①死亡
成年被後見人等の本人の死亡により、後見が終了します。
②家庭裁判所・親族への連絡
本人が死亡した場合、後見人等は家庭裁判所・親族などへ連絡をします。
③後見の終了の登記の申請
後見人等は、法務局へ後見終了の登記を申請します。
④後見の計算(清算事務)
後見人等は任務が終了した場合、2ヶ月以内に在職中に生じた財産の変動を明確にして現在の財産を確定(清算事務)します。後見事務を遂行する過程で生じた財産の変動や、現在の財産状況を明らかにします。
⑤相続人への財産の引渡し
後見が終了すると、後見人は管理していた本人の財産を相続人に引き継がなくてはいけません。
⑥裁判所への報告(後見事務終了報告書の提出)
後見人等は、後見の計算(清算事務)の終了後、すみやかに後見終了の報告を家庭裁判所にします。
成年後見人への報酬支払
後見費用
成年後見人等が後見の事務を行うために必要な費用は、成年被後見人等の本人の負担であり、本人の財産から支出します。成年後見人等が本人と面談をするためにかかった交通費、家庭裁判所への後見事務報告書の送付にかかった通信費などです。
成年後見人等の報酬
家庭裁判所の報酬付与の審判に基づいて、成年被後見人等の本人の財産から家庭裁判所が定めた報酬の支払いを受けます。この報酬付与は、後払いが原則です。
成年後見人等に選任されてから1年後に報酬付与の申し立てを行い、報酬を受け取ります。その後は同様に、1年経過ごとに報酬付与の申し立てを行い、報酬を受け取ります。
公的補助制度
成年後見制度利用支援事業、民事法律扶助制度、公益信託成年後見助成基金などがあり、要件を満たした場合は一定の費用が助成されます。
後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託
成年後見制度の普及とともに、成年後見人による不正行為が増加してきていることから、不正行為を防止するために、後見制度支援信託が導入されました。
一定以上の財産を所有する被後見人については、数百万円程度を手元に残して、残りの金銭は信託銀行に託します。
後見制度支援信託に該当する場合は、司法書士等の専門職後見人が状況を調査した上で、信託するか否かを判断します。
この制度が適用されるのは、成年後見のみです。保佐・補助の類型では適用されません。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝