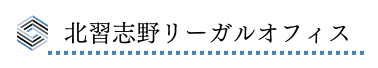遺言書にかけることは?
遺言書にはどのようなことでも書くことができます。
ただ、書いた内容がすべて法的に有効になるわけではありません。
たとえば、「〇〇家の人とは絶交しろ」といった内容は書くことができますが、法的に拘束力のあるものではありませんので、相続人などはその内容に拘束されることはありません。
法的効力をもつ遺言書の内容
遺言書として法的効力をもつ主な内容(遺言事項)は大きく分けて次の3つです。
①身分に関すること
- ・子の認知
-
認知とは、婚姻関係にない男女の間の子(非嫡出子:ひちゃくしゅつし)を自分の子どもと認めることです。
これにより、非嫡出子は相続人となります。
認知は、生前にもすることができますが、遺言ですることもできます。従前までの非嫡出子の相続分は、「法律上の婚姻関係にある男女の間の子(嫡出子)の2分の1」でした。
しかし、この民法の規定が最高裁判所の違憲判決により、平成25年9月5日以後に開始した相続では、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになりました。
なお、平成13年7月以後に発生した相続について、遺産分割がまだ終わっていないなどの未確定の法律関係がある場合などに限定して、平成25年9月5日より前の相続であっても嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になることもあります。 - ・未成年者の後見人や後見監督人の指定
-
未成年者が相続人の場合、親権者である遺言者の死後に親権者がいなくなってしまうときは、未成年の子どもの面倒を見てもらう人を決めておくことができます。
もう一方の親が親権者として存在すれば、後見人の指定をすることはできません。
親権者に代わって、その子の教育、監護、財産管理をするのが「未成年後見人」です。
※未成年後見人には、欠格事由があり未成年者や破産者などはなることができません。
「未成年後見監督人」は、未成年後見人の事務を監督します。
②財産の処分に関すること
- ・相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈)
-
遺言で、相続人以外の人に財産を贈与することができます。
これを『遺贈(いぞう)』といいます。たとえば、長男の妻や事実婚の関係にある内縁の妻などは相続人ではありませんので、財産を譲りたい場合は遺贈をすることになります。
遺贈をする人を「遺贈者」、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
「船橋市〇〇町〇〇番1の土地を〇〇に遺贈する」といったように、具体的に財産を特定して受遺者に遺贈することを、『特定遺贈』といいます。
一方、「相続財産の2分の1を与える」といったように相続分を割合で与えることを、『包括遺贈』といいます。
受遺者は、相続開始後に自由に遺贈を放棄することができ、この場合は法定相続人が相続財産を相続することになります。
特定遺贈の場合は特別な手続きは不要ですが、包括遺贈の場合は、相続放棄と同じ手続きをする必要があります。
相続放棄については、こちらをご覧ください。遺贈は、遺留分減殺請求の対象となります。
→遺留分についてはこちらをご覧ください。遺言者の相続発生前に受遺者が死亡していた場合は、遺贈の効力は発生しません。
そのため、受遺者に子どもがいても相続のように代襲することはできません。
→代襲相続については、こちらをご覧ください。
このような場合に備えて、補充遺贈や後継ぎ遺贈についての内容も遺言書に書いておくとよいでしょう。 - ・財団法人の設立
-
一般財団法人を設立することを遺言で定めることができ、一般財団法人設立登記をすることで法人が設立されます。
設立には300万円以上の財産の拠出が必要です。
遺言で一般財団法人を設立する場合は、次のことを定めておく必要があります。
・財団設立の意思表示
・定款に記載すべき内容(名称、主たる事務所の所在地、目的など)
・遺言執行者 - ・信託の設定
-
遺言によって信託を設定することもできます。
ただし、受託者となる人の承諾が得られない場合など、遺言者の意思どおりの信託とならない可能性もあるので、
生前に信託は設定しておくか、信頼できる受託者の承諾を得ておくきましょう。
※多くの信託銀行で「遺言信託」という商品がありますが、遺言書作成や保管、遺言執行などの財産に関する内容に限って信託銀行が取り扱っているもので、これは遺言で信託の設定をしているのではありません。
→信託についてはこちらをご覧ください。
③相続に関すること
- ・相続分の指定
-
法律で決められた相続の割合(法定相続分)と異なる割合での相続を希望する場合、各相続人の相続分を指定することができます。
たとえば、「相続人である妻の相続分は4分の3、長男の相続分は4分の1とする」などの内容で相続分の指定をすることができます。
相続人の1人だけの相続分を指定した場合、相続分が指定されていないその他の相続人の相続分は、残りの相続財産について法定相続分となります。
遺贈と同様に遺留分減殺請求の対象となります。
上記の例の場合、長男の遺留分は相続財産全体の4分の1です。
遺言書での長男の相続分が4分の1より少ないときは、長男は遺留分の主張をすることができます。
→遺留分についてはこちらをご覧ください。 - ・遺産分割方法の指定
-
具体的に「相続人のだれが」「どの財産を」引き継ぐのかを指定することができます。
たとえば、妻には土地と建物、長男は預貯金、長女には株式と相続させたい場合です。
具体的な財産を相続させるので、土地であれば所在・地番・地目・地積、預貯金であれば銀行名・支店名・口座の種類・番号・利子についてなど相続財産の情報を細かく書いていく必要があります。
遺産分割方法の指定は、プラス財産についてすることができます。
マイナス財産である借金などの債務については債権者との利害関係があり勝手にはできませんので、原則としてマイナス財産は法定相続分で相続することになります。 - ・遺産分割の禁止
-
相続開始から最長5年以内は遺産分割を禁止することができます。
たとえば、相続財産が土地と建物だけのような場合は、遺産分割をすると妻の住居がなくなってしまうことも考えられるため、「少なくとも5年間は実家はそのままにしておくように」などと遺産分割を禁止することが出来ます。
遺言書で遺産分割の禁止がされて遺言執行者がいる場合は、相続人の全員で遺産分割協議が成立しても禁止期間を経過するまでは、遺言執行者の同意がない限り、遺産分割をすることができません。
遺言執行者がいない場合は、相続人全員で遺産分割協議を有効にすることができます。 - ・負担付遺贈
-
子どもに相続財産をあげる代わりに母親の面倒を見てほしいと条件をつけるような条件(負担)付の遺贈をすることができます。
その他にも、遺言者の死後、ペットのことが心配であれば世話を引き受けてくれる人を見つけておいて、ペットの面倒を見てもらうことを条件にすることもあるでしょう。受遺者は、遺贈された財産の価値の範囲内で負担した条件の義務を負います。
受遺者が相続財産を受け取ったにもかかわらず、負担の義務を果たさない場合、遺言の効力は消滅しませんが、他の相続人は受遺者へ負担の履行を請求することができます。
決められた期間内に履行しない場合は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することもできます。遺贈は、受遺者が引き受けるかどうかを決めることができるので、負担付遺贈をする際は、生前に受遺者に話しておきましょう。
- ・相続人の廃除や廃除の取消し
-
相続人の廃除や廃除の取消しは、生前にもすることができますが、遺言でもすることができます。
廃除とは、相続欠格にあたるほど重大でない場合であっても被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えた場合や親不孝や放浪息子のケースなどの著しい非行があった人は、被相続人にとっては自分の財産を相続させたくないこともあるかもしれません。
被相続人の請求や遺言により、家庭裁判所が相続権をはく奪する制度です。
認められない廃除理由もあり、必ず廃除できるわけではありません。 - ・遺言執行者の指定
-
遺言内容を実行させるための遺言執行者を指定できます。
遺言執行者の指定は、遺言でしかすることができません。
子どもの認知、相続人の廃除や廃除の取消しなどは、相続人との利益が相反して相続人が遺言を執行することは不適切であるため、必ず遺言執行者が手続きをします。
遺言執行者が必要な場合に、遺言書に遺言執行者の指定がないときは、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てます。
→遺言執行者についてはこちらをご覧ください。 - ・遺留分の減殺方法の指定
-
遺留分の侵害で遺留分減殺請求権を行使されそうなときに備えて、減殺を行う財産の順序を指定できます。
→遺留分についてはこちらをご覧ください。 - ・特別受益分の控除
- ・保険金受取人の変更
-
保険金受取人の変更は遺言でもすることができます(保険法44条1項)。
被相続人の死亡後、相続人が遺言による保険金受取人の変更があったことを保険会社に通知しないと、
遺言書で保険金受取人に指定された人は、保険会社に対して自分が保険金受取人であることを主張することができません(保険法44条2項)。そのため、相続人が保険会社に保険金受取人の変更があったことを保険会社に通知する前に、元々の契約で保険金受取人と定められていた人が先に保険金を受け取ってしまった場合など、トラブルのもとになりやすいです。
保険金の受取人の変更は、できるだけ生前にするようにしましょう。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝