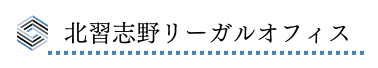遺言書の内容を変更したい・取り消したい
遺言書をつくった後で、内容が間違っていたことに気づいたり、やっぱり書きなおしたいと思うこともあるでしょう。
遺言はいつでも取り消しができるので、何度でも書きなおすことができます。
これを「遺言の撤回」といいます。
遺言書の撤回は、一部の遺言の内容についてでも内容の全部でもできます。
遺言書の作成についても方法が決められていますが、撤回するときにも方法が決まっていて、遺言は遺言で取り消します。
遺言書の取り消しは、どの遺言方式でも可能です。
自筆証書遺言を取り消すには自筆証書遺言でなければいけないという決まりはありませんので、自筆証書遺言を公正証書遺言で取り消すこともできるということです。
遺言の撤回の方法
遺言書の内容を変更したいときや遺言書を取り消したいときは、次のような方法で取り消します。
- ①新しい遺言書をつくる
-
遺言書が2つ以上ある場合は、新しい日付のものが優先しますので、遺言書の内容を変更したい場合は、新たに遺言書を作ります。
新しい遺言書の中に、前の遺言書と矛盾する内容が書いてあれば、その部分は古い遺言書が一部撤回されて新しい遺言書が有効になります。
古い遺言書は、矛盾しない残された部分はいまだ有効なままになります。
少しややこしいですが、たとえば、土地は妻、建物は長男へ相続させるという遺言を父が作成していた場合に、
新しい遺言書で建物は長女へ相続させるという内容を作成したとします。
建物については、前の遺言書と内容が矛盾するので、新しい遺言書が優先して長女が相続します。
一方で土地については、新しい遺言書では何も記載がないので、古い遺言書の土地の部分は有効なままとなり、土地は妻が相続することになります。ですので、もし遺言書の内容の全部を取消したいのであれば新しい遺言書で「遺言者が本日以前に作成した遺言書の全部を取り消す」と書いてわかりやすくしておくべきでしょう。
- ②遺言書の内容に反する行為をする
-
遺言者は、自分の遺言の内容に拘束されないので遺言書の内容に反することでも自由に財産を処分することができます。
この場合、遺言書の内容に反する行為については、遺言書が取り消されたことになります。たとえば、「私が所有する自動車を妻に相続させる」と遺言書に書いたとします。
生前にその自動車を第三者に売ってしまうと、死後に遺言書の内容が実現できなくなり、その売却したという行為が遺言を取り消したとみなされて、その部分において遺言は撤回したことになります。この場合も①新しい遺言書をつくると同様に、遺言者の行為が遺言書と矛盾しない部分については、遺言書は取り消されたことにはまりません。
- ③遺言書を破棄する
-
遺言のすべてを撤回したい場合などは、自筆証書遺言であれば遺言書そのものを破いたり焼いたりして破棄すれば、その遺言は撤回されたことになります。
また、遺言書で相続させることにしていた財産を故意に破棄した場合も、遺言書を破棄したことになります。
ただし、公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されているので、遺言者が保管している正本や謄本を破棄しただけでは撤回できませんので、公証役場に出向いて破棄の手続きをします。
注意事項
遺言の取消権の放棄はできません
遺言の取消しはいつでも自由にすることができますが、それでは困る人もいるかもしれません。
しかし、遺言の取消権の放棄はできないので、遺言書に「この遺言書は取り消すことができない」などの内容を書いても取消権はなくならずに、いつでも自由に取り消しをすることができます。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝