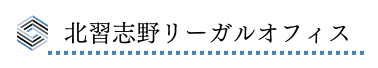誰が相続人になるかは、民法に定められています。(法定相続人)
戸籍などで相続人調査をして法定相続人を確認します。
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。
配偶者は常に相続人
配偶者は、常に相続人になります。
ただし、法律上、被相続人と婚姻関係にない場合(内縁の妻や夫)は相続人になることはできません。
配偶者以外の親族がいる場合は、配偶者とともに
①子、②直系尊属(父母や祖父母)、③兄弟姉妹
の順に法定相続人になります。

相続できる順番と割合は?
相続順位によって相続分が異なる
『相続分』とは、相続することができる割合のことをいいます。
被相続人が遺言で相続分を指定した場合は、
その指定した相続分が優先されます。
しかし、そうでない場合には民法に定められた相続分(法定相続分)が適用されます。
法定相続人の順位
配偶者は常に相続人になります。
そして、配偶者と共に相続人となる人には次のように順番があります。
配偶者以外に相続人となるべき者がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。
①「第1順位の相続人」 被相続人の子→孫→ひ孫(直系卑属)
②「第2順位の相続人」 被相続人の父母→祖父母(直系尊属)
③「第3順位の相続人」 被相続人の兄弟姉妹→甥→姪(傍系血族)
①「第1順位の相続人」→②「第2順位の相続人」→③「第3順位の相続人」の順に優先順位が決まっています。
①第1順位の相続人の子どもがすでに死亡しているときは、
さらに孫、孫が亡くなっていればひ孫というように、代襲(だいしゅう)していきます。
もし、①「第1順位の相続人」が1人もいない場合には、②「第2順位の相続人」が相続人になります。
配偶者以外の異なる順位の人たちが、同時に相続人となることはありません。
相続の割合
民法に定められている各相続人の相続分を、『法定相続分』といいます。
法定相続分は、「相続人の人数」や「第何順位の相続人」か(直系卑属、直系尊属、傍系血族)によって変わります。
法定相続分の考え方は、まず配偶者の取り分があり、その残りを同順位の法定相続人で等分にします。
①第1順位の相続人の場合(法定相続人が配偶者と子ども)
・配偶者の法定相続分 2分の1
・子どもの法定相続分 2分の1を等分
※子どもが2人の場合は、2分の1を2人で等分するので
子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。
②第2順位の相続人の場合(法定相続人が配偶者と父母)
・配偶者の法定相続分 3分の2
・父母の法定相続分 3分の1を等分
③第3順位の相続人の場合(法定相続人が配偶者と兄弟姉妹)
・配偶者の法定相続分 4分の3
・兄弟姉妹の法定相続分 4分の1を等分
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝